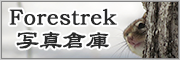2016.2. 4 17:54
最近は節分の日に恵方巻を食べることが一般的になりつつありますが、初午(はつうま)の日というのもあります。
初午の日とは、全国に数万もの社がある稲荷神社の祭日です。
2月に入って初めての午の日(今年は2月6日)に行われ、この日にいなり寿司を食べると縁起がいいと言われています。
稲荷(いなり)といえば、京都の伏見稲荷大社が総本社。
奈良時代の『山城国風土記』には――
秦(はた)一族の先祖である伊呂具(いろぐ)という者が、鏡餅を弓の的にして矢を放つとその餅がハクチョウになって飛び去り、そのハクチョウは山城国に降り立って稲になった。
とあります。
「なんで、餅がハクチョウになって稲?」
なんて疑問はナシ!神話レベルの話しですんで、そこはさらっと流しましょう(笑)
古来、鳥は霊魂の化身であり、中でも白い鳥は特に神聖なものとされていました。しかもハクチョウはツルと共に、稲穂を運ぶ神であり、穀霊であり、稲霊であるとされています。
また、“豊葦原の瑞穂の国”と呼ばれた日本では、稲もまた神聖なもので、米から作られる餅もまたしかり。そんな “神聖なもの同士” の結びつきなのでしょうか。
一部の地域ではいまだにハクチョウと稲は結びついていて、田に降りたハクチョウを殺めるとその家は稲が育たなくなり没落する、とされています。

さて先の矢を放った伊呂具は、その時の殺生を後悔し、稲が生えた所に社を建てて伊奈利社(いなりやしろ)と名付けて敬い、その子孫である秦一族も大切に伊奈利社を信仰したといいます。これが稲荷信仰の元です。
一方、当時は全国各地に土着の農耕信仰があり、キツネを田の神とし神の使者として信仰していました。
キツネは春に田のネズミを食べ、冬になると山に帰ることから、田を守る神だったのです。また、キツネの尾が実った稲穂に似ていることも、神聖視されたひとつと言われています。
すると、当時の有力一族である秦一族が信仰する伊奈利社と、全国各地にあった農耕信仰のキツネ神が稲繋がりで結びつき、キツネが稲荷信仰そのものとなりました。
色々な神仏が結びついて解釈が生まれ、なんでも叶えてくれる万能の神や仏が生まれるわけです。
菩薩や地蔵も元々の仏教的由来など関係なく、庶民にとって万能の仏として信仰を集めた時代があります。
このように庶民にも根付いていった稲荷信仰では、神(キツネ)に供えるためとはいえ、好物のネズミを人間が殺生することはタブーだったため、キツネによってもたらされる米をキツネの好物である油揚げに詰めて “お稲荷さん” として供えるようになりました。
そんなわけで、稲荷神社の祭日の初午の日にはいなり寿司(お稲荷さん)を供え、人間もそれを食することで縁起をあやかる風習となったわけです。
さらに江戸時代には、初午の日に我が子を寺子屋や私塾に入れる風習があり、習い事はこの日に初めるのが良いとされました。
さて、今年の2月6日。
冬の鳥ハクチョウを眺めて、いなり寿司を食べて縁起を担ぎ、何を初めましょう?