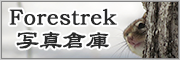2013.7.19 14:35
夏になり、咲いている花々も春モノから夏モノに替わってきています。
突然ですが、
いろんなタイプの人がいて、それぞれにいろんな好みがあるように、
虫にも好みの色があるのをご存知ですか。
受粉を虫に頼る花(虫媒花)にとっては、虫に気に入られることは切実な問題。
どんなに美味しい蜜を用意しても、お目当ての虫が来てくれないと、花粉は運ばれずに子孫を残せない。
気に入ってもらえるためには、自分の花の色をお目当ての虫の好みに合わせるように進化してきました。
春先はアブのような小型の昆虫がまず活動を始めます。
そんなアブの仲間の好みは黄色。
だから春先は黄色の花々が多く咲きます。
だけどもアブの仲間はハチと違ってかなり移り気で気ままなタイプ。黄色と見れば節操なく飛んでいっちゃいます。
ちょっとおバカっぽい感じですね(アブ好きな方がいたらすいません・・・)。
花にとっては、他の種類の花に移動されては受粉が上手くいきません。
だったら、群生しちゃおう、と考えた。
こうなれば、アブが近くの黄色い花に飛び移っても、同じ種である可能性が上がります。
だから、黄色の花の群生って、よく見かけるというわけです。


季節が進み、夏になると紫の花が増えてきます。
紫がお好みなのは、ハナバチの仲間たち。
ハチは社会性昆虫といわれるように、進化の進んだグループ。
賢い堅実家タイプ。ちょっとセレブ。
好みの色が紫、ってのもなんか高級な感じ。
そんなタイプの昆虫はしっかりと堅実にお目当ての花を見分けます。
花にとってはキチンと行儀よく来てもらえるので、群生する必要はありません。
そうなると花は、いかにお目当てのハナバチだけを選別し、他の昆虫に蜜を盗ませないか、を工夫します。
初夏から咲くマメ科の花などは紫が多く、花自体が複雑な形をしていて、花の一番奥の部分に蜜を隠しています。
しかもその蜜は上下の花びらで入り口を隠し、花びらを押し開けて、身体を花に突っ込み、後ずさりができる、
という知力と体力を持ったハナバチだけが得られる報酬となっています。

その上ハチにとって夏は巣の拡張期。エネルギー源となる蜜も大量に必要です。
そんな時期に合わせて花を咲かせた方が確実な来訪が期待できます。
この時期に下を向いて咲く紫の花―チシマアザミの花に、「これでもか!」ってほど花粉をつけられたハナバチを見つけて、
そんな花と虫との巧妙な仕組みを思い出しました。

自分の意思で行動している、と思いきや、好みや行動を読まれて手の上で遊ばされ、
そのうえいつの間にか、手伝いまでさせられて・・・。
世の男性陣も、女性相手に思い当たるフシがあるのではないでしょうか?
まぁ、そんなふうにバカなオトコが気づかず、上手く使われているほうが世の中上手くいくもんで・・・。
「花に虫がやってくる―」
そんなありきたりの光景のウラに、自然の素晴らしい仕組みが隠されています。