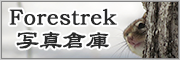2015.8.16 18:30
動植物の名前の由来には色々なパターンがあります。
1、発見場所の地名や発見者・命名者の名前からとるパターン
ヤマハナソウ(札幌市山鼻地区藻岩山で発見されたことから)

チョウノスケソウ(植物採集家須川長之助から)

リンネソウ(分類学者リンネから)

2、見た目から
ネジバナ(花がねじれて並ぶことから)

アカハラ(見たまんま、赤い腹だから)

3、2に近いですが、他の似たものから借用するパターン
ヤブレガサ(破れた傘)

オドリコソウ(編笠を被った踊り子のような花姿から)

カワガラス(川にいるカラスから)

ハナイカリ(錨に似た花姿から)

他にも、生態に基づいていたり、古語に由来したり、訛ってしまって今の名前に変化したものなど、あげたらキリがありません。
また、
「イ」という、ひと文字だけの植物(畳の “い草” ですね)や、

「ヒロハヘビノボラズ」(刺が多くてヘビも登れないことから)といった変わった名前―

別名まで含めると、「リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ(龍宮の乙姫の元結の切り外し)」(=アマモのこと)なんて名前もあります。
ところで、今日は “耳かき” を探してました。
「ムラサキミミカキグサ」

花は3mm程度で、草丈も3~10cm程度の極小な “耳かき” 。
その上、
「湿原内の、初夏までは水に浸かるような場所で、花期の盛夏になると水が干上がるような場所で、だけども乾燥しきることはない場所で―」
という、とても微妙な環境に生育しているようでした。
名前を知るのも楽し、
環境を読み取るのもまた楽し、です。