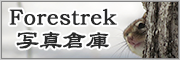2012.4. 6 3:40

先日しっとりとしたツアーをやったばかりなので、今回はしっとりとした投稿で。
雁(ガン)という鳥をご存知ですか?
日本人にとって、渡り鳥の代表とも言うべき鳥のひとつ。
正確にはマガンという鳥で、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北極圏で繁殖し、
冬は両大陸南部に渡って越冬します。
日本にも冬の間、中部地方北部や関東地方北部、東北地方、北海道に多く飛来し、
宮城県伊豆沼には数万羽が飛来、一大越冬地となっています。
今時期は越冬したガンたちが、きたる繁殖に向けて北国へ帰る “北帰行” の時期なのです。
「帰る雁」 は春の季語ともなっていて、悲哀をさそう雁の鳴き声からも、古来からこの鳥にまつわる
民話や伝説、詩歌が数多く詠まれてきました。
江戸時代の採薬使(山野の薬草をとる役人)の書物 『採薬使記』 の、蝦夷地(当時の北海道)に
赴いた際の記録に、「雁風呂」という話が書かれています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青森津軽の浜では毎年秋になると、北からやってきた雁たちが羽を休めていた。
その雁たちは、木の枝をくわえて津軽海峡を渡ってくる。
木の枝は、海上を渡る時にその木を浮かべて休むための“浮き木”。
しばし休んだ雁たちは、くわえてきた木の枝をその地に残し、さらに南の地へと渡っていく―。
そして次の春、雁の北帰行が始まる。
雁は、秋と同じように津軽の浜で休んだのち、秋に自分たちが残していった木の枝を再びくわえて
北の海へ飛び立っていく。
しかし、浜には必ず多くの木の枝が残されるのだった・・・。
残された木の枝の数は、冬の間に日本で死んだ雁の数を意味する。
土地の人は、その情景を悲しく思い、残された木の枝を拾い集め、風呂を焚き、人々に施した。
そうすることが、北に帰れなかった雁への供養なのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というお話。
江戸・上方両方の落語でも似たような噺(はなし)が語られ、つい数年前には某CMにも取り上げられました。
まことに日本的な、「もののあはれ」的な自然観ですね。
どうやら実態は、青森の地に伝わる伝説・民話、というよりか、江戸や上方の人々が雁の悲哀を
津軽の土地と人柄に重ねて伝えた話のようです。
(落語での噺の舞台は函館になっているくらいですし・・・)
また 本来の鳥の行動としては、渡りの際に木の枝をくわえて飛び、
海上で浮き木にして羽を休めながら渡る―、
なんてこともありません。
だけども、そういうツッコミはナンセンス。
江戸時代には、生き物の殺生を戒め、他人に湯を施すことが徳になる、という仏教思想が強くありました。
そこに、毎年決まってやってくる 「雁の渡り」 という自然情景と、人の優しさや功徳を積む大切さ、
などが組み合わさり、ひとつの話として伝えられました。
身近な自然と、生活や思想が密接につながりあっていた時代です。
現代の私達には、こんなふうに自然を感じ取るのはムズカシイですね。
そろそろニセコにも、マガンがやって来て羽を休め、さらなる北帰行に向かいます。
こんなかつての日本人の感覚に想いを馳せて、自然を眺めてみるのもいいかもしれません。