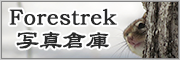2013.1. 3 13:50
前回の「白粉婆」の妖怪話が一部の物好きな方々に思いのほか好評だったので、今回もそんなお話。
断っておきますが、「妖怪」の話であって、「幽霊」話ではありません。
妖怪(化け物)は文化的ですが、幽霊はオカルト的。
妖怪はれっきとした日本文化であり民俗的・自然的ですが、
幽霊=オカルトは自然ガイドの範疇じゃありません。
かの民俗学者・柳田国男は、「妖怪や化け物(オバケ)」と「幽霊」との違いについて、
『化け物は出現する場所が定まっていて、そんな場所に立ち寄らなければ出会わなくてすむが―、
幽霊は足がないにもかかわらず、てくてくと近寄ってくる』
としています。
さらに、
『化け物は相手を選ばず平々凡々の多数の者に向かって交渉を求めるごとくアピールするが―、
幽霊は特定の者にだけ思い知らせようとする』
としています。
出会える時間にしても、
『幽霊は、草木も眠る丑三つ時に戸や屏風を叩いて人を恐ろしがらせる』 が、
『化け物は、多くの人にアピールするために宵や暁の薄暗い時分を選ぶ。
器量のある化け物なら、白昼の明るい頃でも自分の周囲を暗くして出てくる。
草木も眠ってしまうような暗闇では、そもそも “その場所” に人もいないので商売(?)にならんのである』
としています。
化け物が出る黄昏時(タソガレドキ)とは、夕刻のこと。
薄暗い中では、人なのか化け物なのか見分けるのが難しい。
だから「誰ぞ彼は」が転じて、タソガレ。
化け物が跋扈する田舎では、人間と化け物を判別するためにも、
「おばんでございます」と積極的に挨拶を交わす。
そんな挨拶をしない輩は、うさん臭いやつである。化け物と疑ってかかるのである。と。
なるほど、なるほど。
おっと、話しがずいぶんと脱線してしまいました。ワタシのツアーと一緒じゃないの。
そこで本題、訳わからん妖怪―「小豆洗い」。
竹原春泉の記した「絵本百物語-桃山人夜話-」に絵と共に紹介されています。

(妖怪「小豆洗い」 竹原春泉画『絵本百物語』より)
この御仁は、川のたもとで小豆をシャキシャキ洗ってるジジィの妖怪。
なぜか「ジジィ」なのですよ。しかもハゲ頭の。しかもめっぽう猫背の。
このジィさん、川にかかる橋の下で、
『小豆洗おか 人とって食おか シャキシャキシャキシャキ・・・』
などと歌ってるらしい。
そんな音や歌を不思議に思って川に近づくと、水に落ちてしまうとか。
まれに「実際に獲って食われてしまう」という話しが伝わっている地方もあるようですが、
基本的には直接的な悪さをするわけでなく、「いい妖怪」として紹介されているところが多いようです。
確かに、毎日歌を歌いながらせっせと小豆を洗っているだけなら、少なくとも極悪さは感じません。
勤勉なくらい。
「なんで小豆なのー?」とか、
「なんで河原で洗ってるのー?」とか、
「なんでジィさんなのー?」とか、ツッコミどころ満載なのですが、
柳田国男の言うところの、
『相手を選ばず平々凡々の多数の者に向かって交渉を求めるごとくアピール』
しているわけですな。
妖怪の原点をいっているわけです。
そう考えると、けなげな感じすらします。
しかし、アピールの仕方が少々奇抜すぎる気もしますが・・・。
こんなことについてもいろいろと調べてみると、
日本各地にそれぞれ小豆洗いの話しは伝わっていて・・・、
寺の小僧の話しが由来になっていたり、昆虫や獣由来の話しがあったり・・・、
小豆は古来よりその赤い色から魔よけやけがれを払う霊力があると信じられていたり・・・、
スコットランドにも似たような妖精の話しがあったり・・・。
などと、またまた果てしない探求心がくすぐられるわけで・・・。
これについて全部書いていたらタイヘンなことになるので、
興味のある物好きな方は是非ご自分で探求してみて下さい。
あぁぁ、また自然ガイドらしい自然の話を書かなかったなぁ・・・。